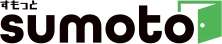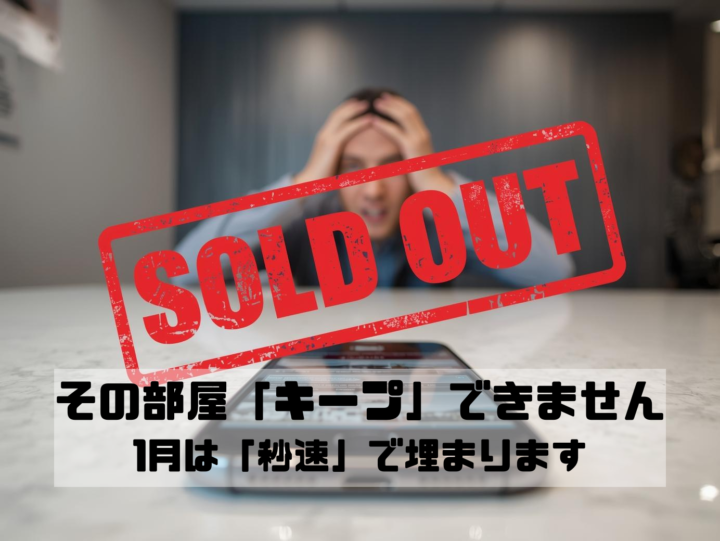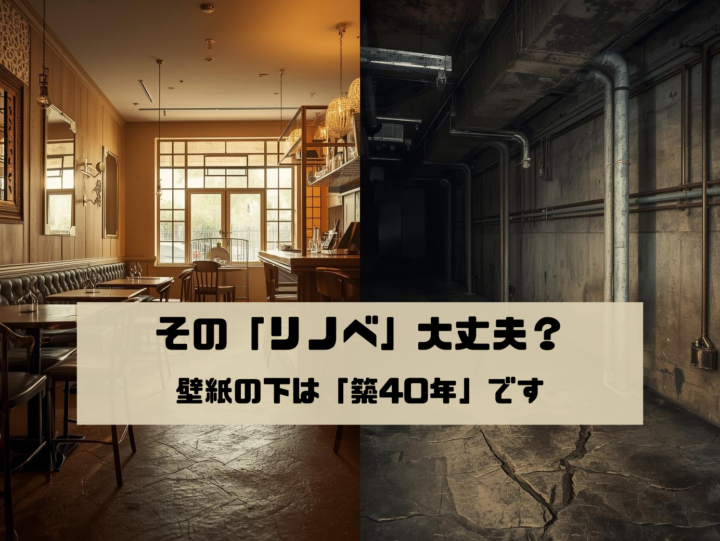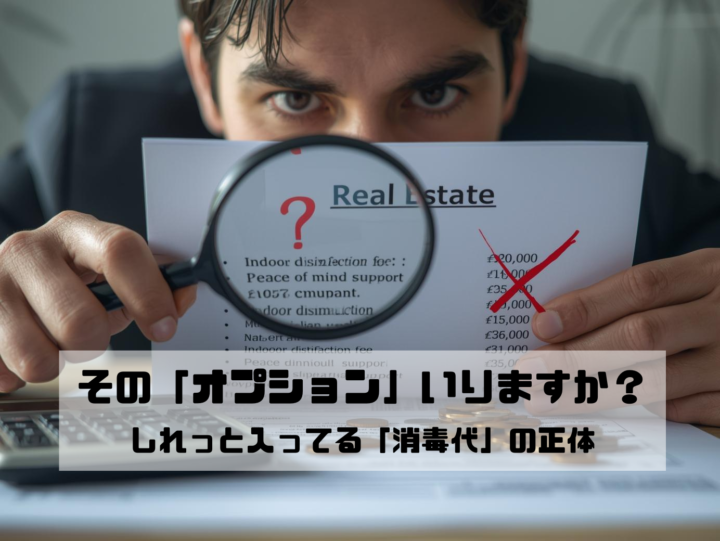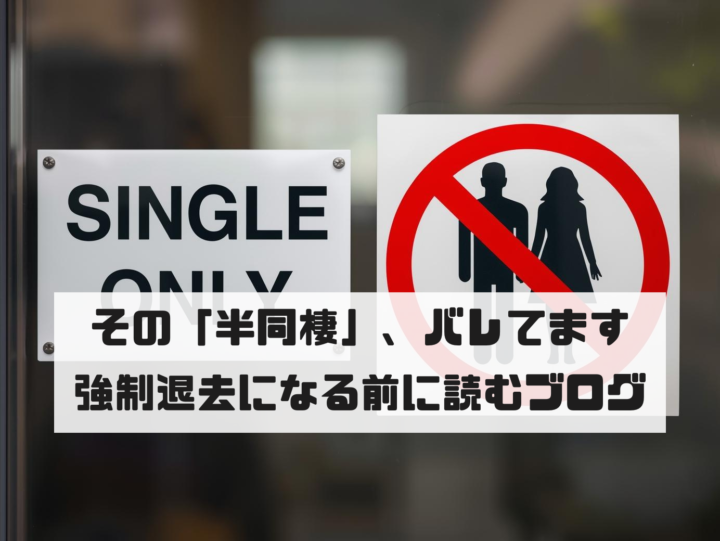「親から相続した土地を売りたいけれど、いくら税金を払うことになるの?」
たとえば、60代で岡山の実家の土地を相続したAさんが、評価額2,000万円で売却を検討しているとします。土地を売って利益(譲渡益)が出る場合、譲渡所得税(所得税+住民税)という税金がかかります。しかし、計算方法が複雑なうえ、場合によっては他の税金も発生するため、「結局いくら納めることになるのか分からない…」と不安になる方も多いでしょう。また、土地を売却する際に税金を抑える特例があるのかも気になるところです。
そこで本記事では、2,000万円の土地売却でかかる税金について、主な税目や計算方法を専門家目線で分かりやすく解説します。さらに、ケース別の税額シミュレーションや、知っておきたい節税のポイント3選、そしてよくある質問への回答も紹介します。不動産売却の経験が少ない方でも理解できるよう、短い文章とリストを活用して整理しました。ぜひ事前に税額を把握し、売却後の手取り額の計画に役立ててください。
土地売却で発生する主な税金の種類
土地を売却するときに関係する税金には、主に次の3種類があります。
- 印紙税(いんしぜい) – 売買契約書に貼る収入印紙代として納める税金です。契約書の記載金額に応じて定められており、たとえば土地売買価格が2,000万円の場合、契約書1通につき印紙税2万円が必要です 。※この金額は令和9年3月31日までの軽減措置後の税率です。
- 登録免許税 – 登記(権利の登録変更)をするときにかかる税金です。土地を売却する際は、住宅ローンの抵当権抹消登記をするケースが多く、不動産1個につき1,000円の登録免許税が課税されます 。たとえば一戸建てを売る場合、土地と建物それぞれに抵当権が付いていれば計2,000円が必要です。
- 譲渡所得税(じょうとしょとくぜい) – 不動産を売却して利益が出たときに課される税金です。個人の場合、所得税(国税)と住民税(地方税)の2つで構成され、合わせて課税されます。譲渡所得税は売却益に対してかかるため、利益が出なければ発生しません(詳しくは後述)。
以上のうち、印紙税と登録免許税は売却時に必ず発生します。一方、譲渡所得税は売却益が出た場合のみ課税されます。それでは、もっとも金額が大きくなりがちな譲渡所得税について詳しく見てみましょう。
譲渡所得税(所得税・住民税)の計算方法とポイント
土地を売って譲渡益(売却益)が出た場合、その利益部分に対して所得税と住民税がかかります。譲渡所得税の額を求めるには、まず**譲渡所得(課税譲渡所得)**を計算しましょう。計算式は以下のとおりです。
- 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費+譲渡費用)
取得費とは、その不動産を買ったときにかかった費用です。具体的には購入代金や購入時の手数料、建物がある場合は建築費用から減価償却相当分を引いた額などが含まれます 。譲渡費用とは、売却時に直接かかった費用のことで、不動産仲介会社に支払う仲介手数料、売主負担の印紙税、売却のために建物を解体した費用(古家の取壊し費用)や、立ち退いてもらうための費用(立退料)などが該当します。
譲渡所得が計算できたら、その金額に税率を乗じて所得税額・住民税額を算出します(※譲渡所得税は給与所得とは分離して計算されます)。税率は不動産の所有期間の長さによって異なり、売却した年の1月1日時点で5年を超えるかどうかで区分されます。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下) … 税率 39.63%(内訳:所得税30.63%+住民税9%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超) … 税率 20.315%(内訳:所得税15.315%+住民税5%)
※上記税率には復興特別所得税を含みます。短期譲渡の税率は長期譲渡の約2倍となり、大きな差があります。5年ちょうどで売却する場合は注意が必要です。所有期間の起算日は取得日ではなく毎年1月1日時点なので、たとえば2018年8月に取得した土地を2023年10月に売却しても、2023年1月1日時点では4年余りの保有となり短期譲渡扱いになります。
以上が譲渡所得税の基本的な計算方法です。続いて、実際に2,000万円で土地を売却した場合の税額を具体的なケース別に試算してみましょう。
2,000万円の土地売却でかかる税金【ケース別シミュレーション】
同じ2,000万円で土地を売却する場合でも、**条件次第で税額は大きく変わります。**ここでは典型的な4つのケースについてシミュレーションしてみます。
ケース1:長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合
≪条件≫(例:8年前に購入した土地を売却)
- 売却価格:2,000万円
- 取得費:500万円(購入代金および諸経費)
- 譲渡費用:50万円(仲介手数料等)
- 所有期間:8年(長期譲渡所得に該当)
- 抵当権抹消登記:必要あり(※住宅ローン完済のため)
≪税額試算≫(長期譲渡所得税率20.315%を適用)
- 譲渡所得 = 2,000万円 - (500万円+50万円) = 1,450万円
- 譲渡所得税 = 1,450万円 × 20.315% = 約294万5,000円(所得税+住民税の合計)
- 登録免許税 = 1,000円(抵当権抹消の登記)
- 印紙税 = 2万円(売買契約書1通・軽減税率適用後 )
≪合計税額≫:約 296万円(2,945,000円+1,000円+20,000円)
長期譲渡のケースでは、概ね300万円弱の税負担となる計算です。なお、このほかにも不動産会社へ支払う仲介手数料(売買価格の3%+6万円が上限)や、司法書士に依頼する場合の報酬などが別途かかります。
ケース2:短期譲渡所得(所有期間5年以下)の場合
≪条件≫(例:3年前に取得した土地を売却)
- 売却価格:2,000万円
- 取得費:1,000万円
- 譲渡費用:50万円(仲介手数料 等)
- 所有期間:3年(短期譲渡所得に該当)
- 抵当権抹消登記:必要あり
≪税額試算≫(短期譲渡所得税率39.63%を適用)
- 譲渡所得 = 2,000万円 - (1,000万円+50万円) = 950万円
- 譲渡所得税 = 950万円 × 39.63% = 約376万400円
- 登録免許税 = 1,000円
- 印紙税 = 2万円
≪合計税額≫:約 378万円(3,760,400円+1,000円+20,000円)
短期譲渡所得の場合、税率が高いため支払う税金も大きくなります。同じ2,000万円の売却でも、長期譲渡のケース1より80万円以上も税額が増えている点に注目してください。
ケース3:所有期間10年以上・マイホーム売却の場合(軽減税率の特例)
≪条件≫(例:築古の実家を解体し、更地で売却)
- 売却価格:8,000万円(更地にして売却)
- 取得費:500万円
- 譲渡費用:800万円(古家の取壊し費用等)
- 所有期間:12年(マイホームとして使用)
- 適用特例:居住用財産(マイホーム)を売ったときの軽減税率の特例 (※10年以上所有したマイホームが対象。譲渡益6,000万円以下部分の税率が優遇されます )
≪税額試算≫(軽減税率適用後)
- 譲渡所得 = 8,000万円 - (500万円+800万円) = 6,700万円
- 譲渡所得税(※軽減税率)
- 6,000万円までの部分:6,000万円 × 14.21% = 852万6,000円
- 6,000万円超過分:700万円 × 20.315% = 142万2,000円
- 合計= 994万8,000円(約995万円)
このケースでは、本来であれば通常の長期譲渡税率20.315%で約1,360万円課税される計算ですが、軽減税率の特例により約995万円まで税負担を抑えられます。10年超所有のマイホームを売却する場合は、ぜひこの制度を活用しましょう(要件を満たせば譲渡所得から3,000万円控除する特例とも併用可 )。
ケース4:取得費が不明な場合(相続で取得した土地など)
≪条件≫(例:親から相続した古い土地を売却)
- 売却価格:2,000万円
- 取得費:不明(※購入時の資料がない)
- 譲渡費用:100万円(仲介手数料・古家解体費用 等)
- 所有期間:8年(長期譲渡所得に該当)
≪ポイント≫:取得費が分からない場合、税法上売却価格の5%を取得費にできます 。本ケースでは取得費=100万円(2,000万円の5%)として計算します。実際の取得費が5%より小さい場合も5%を採用可能ですが、通常は5%では少なすぎて課税額が大きくなる点に注意が必要です。
≪税額試算≫(取得費5%で算出)
- 概算の譲渡所得 = 2,000万円 - (100万円+100万円) = 1,800万円
- 譲渡所得税 = 1,800万円 × 20.315% = 約365万7,000円
取得費が不明だと、上記のように利益が大きく計算されて税金も高額になる傾向があります。たとえば実際には取得費が数百万円あったとしても、証拠書類がなければ5%(=100万円)しか認められません。その結果、ケース1(取得費500万円の場合)の約296万円よりも多い約366万円もの税金を支払うことになりかねません。こうした事態を避けるためにも、相続した土地を売却する際は過去の売買契約書や領収書を探し、少しでも取得費を実額で証明できるようにしておくと良いでしょう。
以上のシミュレーションから、2,000万円で土地を売却した場合の税金はケースによって約300万円~380万円前後と幅があることがわかります。では、こうした譲渡所得税を少しでも抑える方法はあるのでしょうか?次の章で、土地売却時の主な節税策を3つ紹介します。
2,000万円の土地売却で税金を抑えるための3つのポイント
不動産売却では適用できる特例やタイミング調整によって、税負担を軽減できる可能性があります。主な節税ポイントは次の3点です。
- 所有期間を5年超にしてから売却する (短期より長期譲渡の税率が有利)
- 「3,000万円特別控除」を利用する (居住用財産を売った場合の特例)
- 相続した土地は「空き家の3,000万円控除」を検討 (被相続人の居住用財産売却の特例)
以下で、それぞれの内容をもう少し詳しく見てみましょう。
1.所有期間が5年を超えてから売却する
前述のとおり、不動産の譲渡所得税は所有期間5年で税率が大きく変わります。5年超の長期譲渡に該当すれば税率約20%で済みますが、5年以下の短期譲渡だと約39%もの税率が課されます。できるだけ手取りを残したい場合、購入(または相続)から5年以上経過したタイミングまで売却を待つのが有効です。
ただし、所有期間のカウントには注意しましょう。冒頭のケースでも触れたように、売却年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断されます。取得日から単純に5年経過しただけでは足りない場合があるので、誤った判断をしないようお気を付けください。正確な判定やシミュレーションは不動産会社や税理士など専門家に相談すると安心です。
2.居住用財産の「3,000万円特別控除」を活用する
自分が住んでいた家や土地(マイホーム)を売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります 。これを**「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」といい、適用できれば譲渡益が3,000万円まで非課税**になります。仮に譲渡益が2,000万円で収まるなら、控除によって譲渡所得税はゼロになる計算です。
ただし本特例を受けるにはいくつかの要件があります。主な条件の例を挙げると:
- 自分が住んでいた住宅や敷地であること(空き家を取り壊して土地だけ売る場合、取り壊しから1年以内の売却であること等)
- 売却した年の前々年・前年に同様の特例を使っていないこと
- 売却先が親族など特別な関係者ではないこと など
※適用条件の詳細は国税庁のホームページをご確認いただくか、専門家へお問い合わせください。要件を満たせば非常に強力な節税策なので、マイホームを売る方はぜひ検討しましょう。
3.相続した土地は「空き家の3,000万円特別控除」を検討する
親から相続した家や敷地を売却する場合には、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除」という特例制度が利用できる可能性があります 。これは、いわゆる空き家の発生を抑制するための特例措置で、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。
適用される主なケース・条件の一例:
- 被相続人(亡くなった方)が一人暮らしをしていた住宅とその土地であること(マンション除く、昭和56年5月以前建築の旧耐震家屋 等)
- 古い家屋を取り壊して更地で売却するか、耐震リフォーム等で基準を満たした上で家屋付きで売却すること
- 相続開始から3年後の年末までに売却が完了していること
上記は代表的な条件ですが、他にも細かな要件があります。また2024年以降の譲渡では相続人が3人以上いる場合、控除額が2,000万円に減額されるなどの改正も行われています 。該当しそうな方は最新の制度内容を確認し、適用可否を判断するとよいでしょう。
2,000万円の土地売却と税金に関するよくある質問
最後に、2,000万円の土地を売却する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 譲渡所得税がかからないケースはありますか?
A. はい、いくつか考えられます。まず、売却益が出なかった場合(譲渡所得がゼロまたはマイナス)には所得税・住民税は課税されません。たとえば買ったときより安値で土地を手放した場合や、売却益が仲介手数料などの費用で消えてしまった場合です。また、上で紹介したような特別控除を利用して譲渡益が0円まで圧縮できれば、その場合も譲渡所得税はかかりません。極端な例では、マイホームの3,000万円控除を使って譲渡益2,000万円が全額控除されれば、所得税・住民税とも非課税になります。
Q2. 相続した土地を売却した場合、税額は変わりますか?
A. 相続で取得した土地を売る場合、計算上の取得費が低くなりがちな点に注意が必要です。取得費が不明なケースでは売却代金の5%しか見做し経費にできないため、結果的に譲渡益が大きくなって税額も増える傾向があります 。一方で、前述の相続空き家の3,000万円控除が適用できれば大幅な節税になります 。例えば亡くなった親御さんが一人で住んでいた家を相続し、更地にして早期に売却すれば、譲渡益から最大3,000万円が控除される可能性があります。相続土地を売る際は、通常の特例に加えてこの空き家特例も検討するとよいでしょう。
Q3. 税金がまったくかからない土地の売り方は存在しますか?
A. 残念ながら、完全に税金ゼロで土地を売る方法はありません。なぜなら、譲渡所得税が発生しない場合でも印紙税または登録免許税のいずれかは必ず発生するからです。売買契約を締結する以上、契約書に貼る収入印紙(印紙税)は必要ですし、抵当権の有無にかかわらず所有権移転登記をすれば名義変更の登録免許税がかかります。また利益が出た場合には譲渡所得税も課税されます。ただし逆に、利益が出なければ譲渡所得税は課税されないため、諸費用を差し引いてプラスが残らないよう調整する(極端に安値で売る等)ことで所得税・住民税をゼロにすることは理論上可能です。しかし現実的には、税金を理由にわざわざ不利な価格で売却するのは本末転倒でしょう。大切なのは各種税金を正しく理解した上で手取り額を試算し、納得できる形で売却することです。
まとめ:土地売却前に税金シミュレーションをして備えよう
2,000万円で土地を売却したときに発生する税金について、主要な税目の解説からケース別の試算、節税のコツまで詳しく説明してきました。思った以上に税額が大きく感じられたかもしれません。しかし、事前にシミュレーションしておけば売却後の手取り額を把握でき、資金計画も立てやすくなります。また、適用できる特例の有無によって納税額が大きく変わるため、ぜひ売却前に条件を確認してみてください。
土地を少しでも高く売りたい場合、そして複雑な税金の悩みを解消したい場合は、信頼できる不動産会社に相談することがポイントです。経験豊富な不動産会社であれば、税金面の不安も含めて丁寧にアドバイスしてくれるはずです。特に相続案件に強い会社だと、税理士と連携して節税策を提案してくれることもあります。
私たちTorus不動産合同会社(岡山県岡山市北区)でも、不動産売却に関する無料相談や査定依頼を随時承っております。 地域密着の不動産会社として、岡山エリアの市場動向を踏まえた適正な査定はもちろん、売却にかかる費用・税金の試算についてもしっかりサポートいたします。複数社の査定を比較検討したい場合のアドバイスも可能です。「実際に売ったら手元にいくら残るのか知りたい」「税金について詳しく教えてほしい」といったご要望がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。納得のいく土地売却ができるよう、専門家チームが全力でお手伝いいたします。