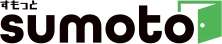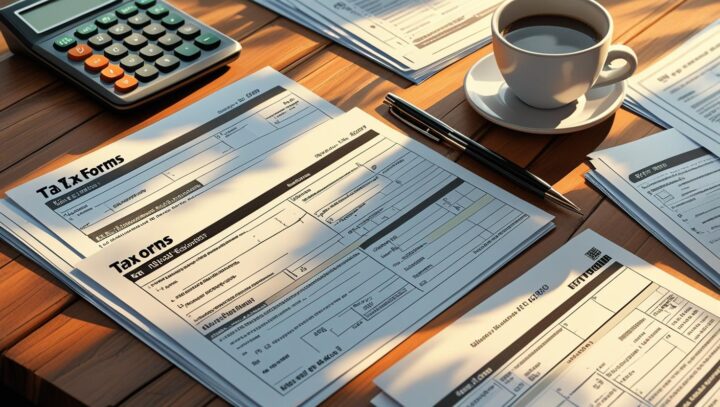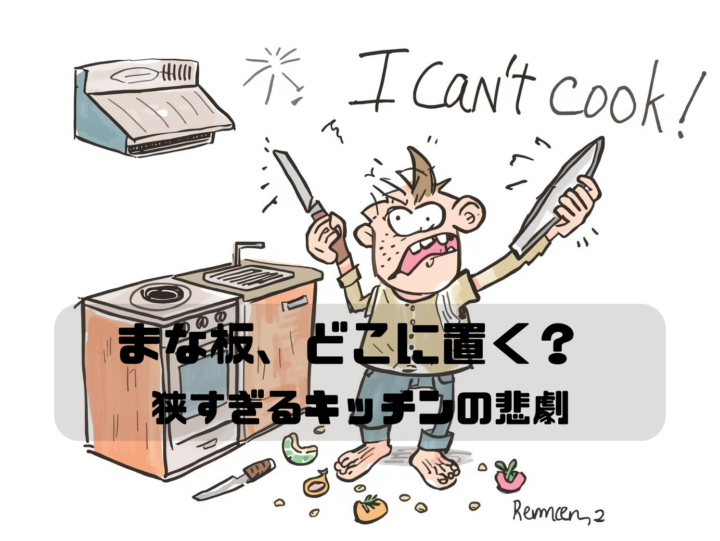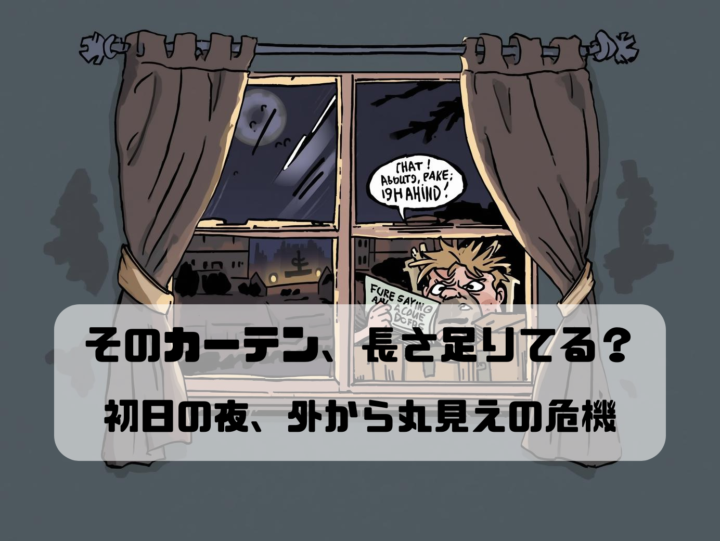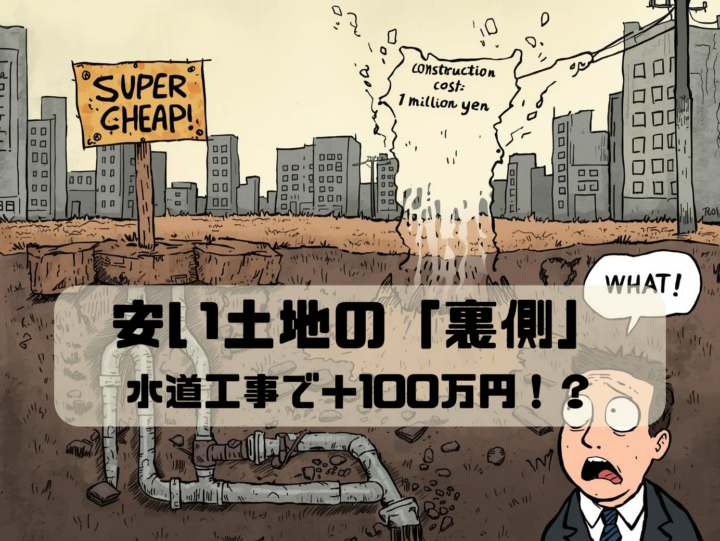この記事のハイライト
● 不動産売却でかかる税金は主に「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」の3つ。
● 最も重要な「譲渡所得税」は、売却益(譲渡所得)に所有期間で変わる税率をかけて計算する。
● 「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」などを活用すれば、大幅な節税が可能。
● 税金の計算や特例の適用は複雑。岡山市の不動産事情に詳しいプロへの相談が成功のカギ。
岡山市で不動産の売却をお考えの際、「一体いくらで売れるんだろう?」という売却価格に目が行きがちです。しかし、思わぬ落とし穴となるのが「税金」。売却後に「こんなに税金がかかるなんて知らなかった…」と後悔しないためにも、税金の知識は不可欠です。
今回は、不動産売却でかかる税金の種類から、初心者でもわかる具体的な計算方法、そして知らないと損をする賢い節税対策まで、岡山市の不動産売却を専門とするプロが徹底解説します。
※本記事は2025年2月時点の税制に基づいて作成しています。税法は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁のホームページ等でご確認いただくか、専門家にご相談ください。
1. 【基本のキ】不動産売却でかかる税金は3種類
まずは、どのような税金がかかるのか全体像を把握しましょう。不動産売却時にかかる主な税金は以下の3つです。
種類1:印紙税
印紙税は、売買契約書に対して課される税金です。契約書に記載された売買金額に応じて税額が決まり、収入印紙を貼り付けて納税します。一般的に、売主様と買主様がそれぞれ保管する契約書1通ずつ、計2通を作成するため、ご自身の保管分にかかる印紙税を負担します。
| 契約金額 | 税額(本則) | 軽減税率適用後の税額 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※不動産売買契約書にかかる印紙税は、2027年3月31日まで軽減措置が適用されます。
最近では電子契約も増えており、その場合は課税文書の作成にあたらないため印紙税は不要です。節税の一つの方法として覚えておくと良いでしょう。
種類2:登録免許税
登録免許税は、法務局で不動産の権利関係を記録する「登記」手続きの際に発生する税金です。売主様が負担するのは主に**「抵当権抹消登記」**にかかる費用です。
住宅ローンを利用して購入した不動産には、金融機関の「抵当 権」が設定されています。売却時には、ローンを完済してこの抵当権を抹消する必要があり、その手続きに登録免許税がかかります。
費用は不動産1つにつき1,000円です。土地と建物であれば、合計2,000円となります。通常は司法書士に手続きを依頼するため、別途1〜2万円程度の報酬が必要です。
種類3:譲渡所得税(所得税・住民税)
不動産売却における税金の主役であり、最も金額が大きくなる可能性のあるのが譲渡所得税です。これは、不動産を売却して得た利益、すなわち**「譲渡所得」**に対して課される税金で、「所得税(復興特別所得税を含む)」と「住民税」を合わせた総称です。
譲渡所得がマイナス(つまり損失が出た)場合は、譲渡所得税はかかりません。節税のポイントは、この「譲渡所得」をいかに正しく計算し、特例を使って圧縮できるかにかかっています。
2. 【最重要】譲渡所得税の計算方法を3ステップで完全ガイド
譲渡所得税の計算は少し複雑に見えますが、以下の3つのステップに沿って進めれば、ご自身のケースを当てはめて理解できます。
Step 1:売却の利益「譲渡所得」を計算する
まずは、税金の元となる利益(譲渡所得)を算出します。
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
- 売却価格(譲渡収入):買主様から受け取る売却代金そのものです。
- 取得費:その不動産を購入したときにかかった費用のこと。土地・建物の購入代金や、購入時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などが含まれます。
- 注意点① 建物の減価償却:建物は年数と共に価値が減少するため、購入代金からその減少分(減価償却費)を差し引く必要があります。
- 注意点② 取得費が不明な場合:先祖から受け継いだ土地などで取得費が分からない場合は、**売却価格の5%**を「概算取得費」として計算できます。
- 譲渡費用:今回の売却のために直接かかった費用のこと。仲介手数料や印紙税、抵当権抹消登記費用などがこれにあたります。
Step 2:不動産の「所有期間」を確認する
次に、売却した不動産をどれくらいの期間所有していたかを確認します。この所有期間によって、次に説明する税率が大きく変わるため非常に重要です。
- 短期譲渡所得:所有期間が5年以下の場合
- 長期譲渡所得:所有期間が5年超の場合
【超重要ポイント】 所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断します。例えば、2019年8月に購入した不動産を2025年3月に売却した場合、暦の上では5年を超えていますが、2025年1月1日時点ではまだ5年以下と判断され「短期譲渡所得」となります。
Step 3:税率をかけて税額を計算する
最後に、Step1で算出した譲渡所得に、Step2で決まった所有期間に応じた税率をかけます。
譲渡所得税額=譲渡所得×税率
| 所有期間 | 区分 | 税率(所得税 + 住民税) |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% (所得税30.63% + 住民税9%) |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% (所得税15.315% + 住民税5%) |
ご覧の通り、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が約2倍も変わります。売却のタイミングを検討する上で、この「5年の壁」は必ず意識しましょう。
3. 【知らないと損】不動産売却の税金を賢く抑える節税対策5選
高額になりがちな譲渡所得税ですが、条件を満たせば利用できる強力な特例(控除)があります。ここでは代表的な節税対策を5つご紹介します。
対策1:マイホーム売却の王道!「3,000万円の特別控除」
ご自身が住んでいたマイホームを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。多くのケースで適用でき、最も節税効果が高い制度です。
この特例を使えば、譲渡所得が3,000万円以下の場合、譲渡所得税は0円になります。
主な適用要件は、「自分が住んでいる家屋を売る」「住まなくなってから3年後の年末までに売る」などがあります。
対策2:所有期間10年超のマイホームなら「軽減税率の特例」
売却したマイホームの所有期間が10年を超えている場合、さらに有利な軽減税率を適用できます。この特例は、上記の**「3,000万円の特別控除」と併用可能**です。
| 課税譲渡所得 | 税率(所得税 + 住民税) |
| 6,000万円以下の部分 | 14.21% (所得税10.21% + 住民税4%) |
| 6,000万円超の部分 | 20.315% (所得税15.315% + 住民税5%) |
3,000万円を控除した後の譲渡所得が6,000万円以下であれば、長期譲渡所得の税率(20.315%)よりもさらに低い税率が適用されます。
対策3:相続した不動産を売るなら「取得費加算の特例」
相続で取得した不動産を、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合、納付した相続税の一部を不動産の取得費に加算できる特例です。取得費が大きくなることで譲渡所得が圧縮され、結果的に譲渡所得税を抑えることができます。
対策4:もし損失が出ても諦めない!「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
不動産を売却して利益が出るどころか、損失(譲渡損失)が出てしまった場合でも、税金が戻ってくる可能性があります。マイホームの買い換えなどで一定の要件を満たす場合、その損失を給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できます。さらに、その年に控除しきれなかった損失は、翌年以降最大3年間にわたって繰り越すことができます。
対策5:最も確実な対策は「専門家への相談」
これらの特例は、それぞれ適用要件が細かく定められています。どの特例が利用できるか、またどの特例を使うのが最も有利かは、個々の状況によって大きく異なります。「自分で判断して申告したら、もっと節税できる方法があった…」という事態を避けるためにも、税理士や不動産のプロに相談することが最善の策です。
4. まとめ
不動産売却では、印紙税や登録免許税、そして最も重要な譲渡所得税がかかります。特に譲渡所得税は、計算方法や所有期間の考え方が複雑で、高額になりやすい税金です。
しかし、「3,000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」といった制度を正しく理解し活用することで、納税額を大きく抑えることが可能です。ご自身の状況でどの特例が使えるのか、いつ売却するのがベストなのかを見極めることが、賢い不動産売却の第一歩と言えるでしょう。
岡山市南区・中区・北区・東区をはじめ、岡山市全域の不動産売却ならTorus不動産へ。 土地・一戸建て・マンションから収益物件、農地まで、幅広い不動産売却の実績がございます。複雑な税金の話や節税対策についても、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適なご提案をいたします。 無料査定も実施しておりますので、「まずは税金のことだけ相談したい」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談ください!